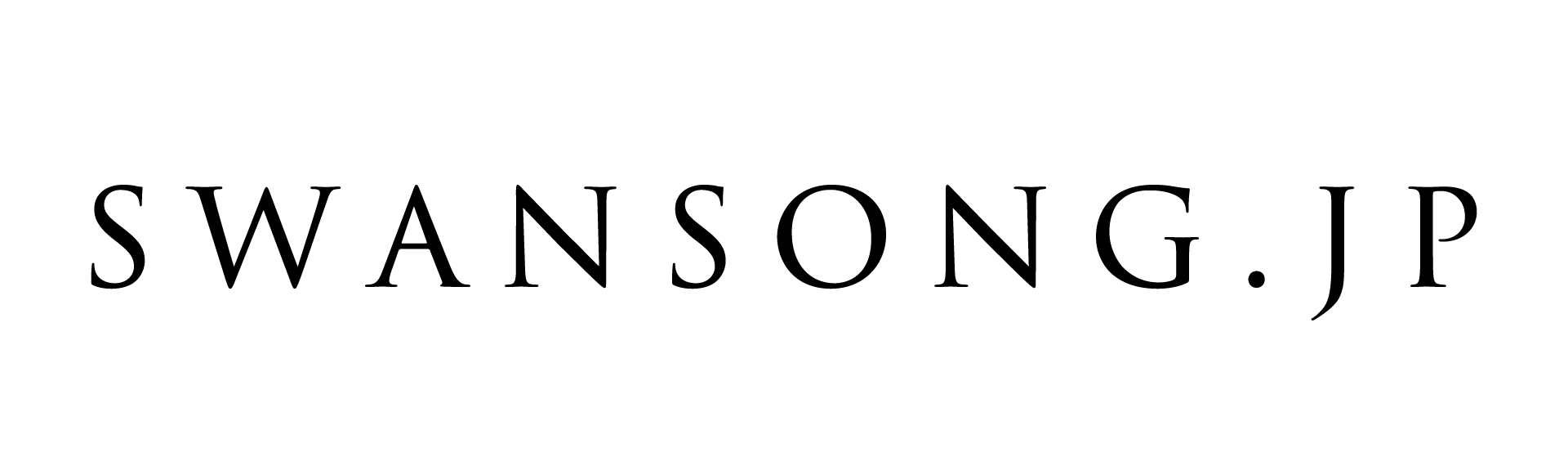震災の後を生きていこうとする若者の姿も描いた『おかえりモネ』。ちょうど8時15分に家を出るスケジュールがこの一年だけ生じたこと、そこにずっと活動を追ってきたアイドルが出演すること、タイミングが偶然噛み合って、この作品は生涯記憶に残るであろう作品になった。
同窓会会報に寄稿する文章を色々検討していた時に、最終的に寄稿した文と文章の趣旨は基本的に同じではあるものの、具体例として『おかえりモネ』に着眼したバージョンも作っていたので、それをここに残したいと思う。
= = = = =
本作は、実に様々な読みに耐えうる脚本の丁寧さを持ち合わせている作品だと思いますが、この稿では「傷」ということにクローズアップしてみたいと思います。この作品では、主題歌『なないろ』の歌詞にも出てくる「傷」自体やそれと向き合うというテーマが通奏低音を成しています。
大人に救われるべき震災時に手を差し伸べてもらえなかった子どもは、その傷を抱えたまま、いち早く大人になって自助に努めながら周りを助けることを余儀なくされます。主人公の百音が気象予報士を目指す原動力となった「役に立たないと」という強迫観念も「自分が自分でいる、ただそれだけでいい」と思えなくなる子供の頃の経験が響いているように思えてなりません。こういった傷は、外部から押し付けられる「節目」などとは関係なく残るもので、「けりをつける」などといった言葉で片づけられるような単純なものではありません。
百音の同級生たちは、この傷を抱える中で、徐々に家族や友人間で震災のことを話さなくなります。同級生の一人である亮のセリフ「話しても地獄、話さなくても地獄」が端的に表すような深刻な状況だからこそ、やむを得ず発話という勇気のいる行動を起こさない方へと流れていってしまうのです。
その問題に触れることがタブー化されてしまい、問題が長期的に解決されないままになってしまう。これを描いたシーンをみて、私は高校在学中に課題研究で学んだ水俣について思い出しました。朝ドラはあくまで物語ですが、水俣でタブー化が起きていたというのは現実の出来事です。ここで私は、傷はそれ自体が痛いだけではなく、それを語れないという痛みをも併せ持ちやすいということに気付きました。
亮の「話しても地獄」という言葉は、主に2つのニュアンスをもつように思います。
まず、話すことにより傷を一人で抱え込まなくなりある程度癒えるところまでいったとしてもその原因となった問題(この作品でいえば家庭の経済的困窮、父の抱えるアルコール依存症、津波に遭った母がずっと行方不明であること等)が雲散するわけではない「地獄」というニュアンスが挙げられるでしょう。幼い頃皆で手を繋いでUFOを呼ぼうとした経験について亮は、もう祈ってもUFOは来ないし自分たちは一生このままだと諦観を示しますが、同級生の後藤はすぐに、これからもUFOは呼べるし、自分が見た以上UFOは確かに来るし、みんなで祈れば叶うんだと反論します。たとえ何の証拠が無くても、心がある限り祈り続けることはできます。お互いの傷を話したところで100%分かり合えはしないし、お互いの傷を知ったうえで苦しみのない未来を共に祈ったところで直接状況が好転するわけではありませんが、その祈りは各々違う痛みをもったまま手を携えて明日へ歩んでいくうえで必要な共通の基盤にはなるのです。祈りでなら人々は同じ次元で通じ合えるのです。また一方でこの作品は一貫して、誰しも何らかの痛みを持ち、しかもその痛みの大きさは比較できないと語り続けてもいます。特にこのパンデミックの中では、納得いかないけれどもやむを得ず何らかの犠牲を払った傷は誰にでもあるはずですが、その傷を他人の傷と比べて小さそうだからといって引っ込める必要はなく、またそうした傷を語ることは決して「かわいそう」なことではないのだと、この作品は教えてくれます。
次に、話すだけ“空気”が悪くなり、困難の中でかろうじて繋がっていた話し手・聞き手の関係が壊れてしまう「地獄」というニュアンスも考えられるでしょう。これは聞き手の状態が整っていないことが大きな原因だと私は思います。たとえばこの作品でいえば、子どもから震災で受けた傷のことを話されたときに、聞き手である親が、あたかもその傷を治さなかったことを責められているように解釈したり、またこれからその傷を癒してほしいという頼みのように解釈することによる「地獄」を生む可能性があるから、子供は話さなくなるのです。聞き手の側が、責任がどこにあったかやどう治すか(過去・未来)の話と今そこにある傷の痛みの話とを切り離し、あくまで現在に即して傷に寄り添うことができれば、このような「地獄」は生まれないでしょう。また「共感」と「同情」の使い分けもまた聞き手に求められる能力の一つであるように思います。個人的には、バラバラの二者が想定されている「共感」という言葉に対して、「同情」という言葉には一体になることが想定されているイメージを抱いており、この同情というのは、他人と一体になった気分になりながら、結局経験に基づいた「自分の論理」に基づいて相手に起きた出来事を解釈し、一体になったのを良いことに相手に成り代わって痛みの度合いをジャッジすることに繋がりかねない気がするのです。世間には「男はアドバイス、女は共感」などという様々な意味で不愉快な言い回しがありますが、そもそも共感とアドバイスは対置されるものではなく、まず痛みへの共感が根本にあって、そのうえで「私だったらこうする」「それはこう捉えるべきじゃない?」というアドバイスのあるなしを決めていくべきでしょう。共感に基づかないアドバイスはただの押し付けです。そしてまた、ここでいう共感というのは、自分のことのように関心を持ちながら相手の痛みはあくまで相手の手中にとどめたまま相手の解釈ごと痛みそのものを引き受けようとする種の共感であると思います。「カウンセリングに行く習慣が定着していない」と言われがちな日本に住んでいる私は、「傷を語ること」をどこか遠くのものだと思い、こうした話題が振られた際どう反応すればいいか分からない部分があるように思います。ですが、普段は見えていないが自他問わず誰かに生じ得る痛みについて日頃から考慮に入れることを怠らなければ、この分からなさは乗り越えていけるはずだと信じています。そのように行動することは、きっと自分を守るためにもなるでしょう。
= = = = =
寛解をめざして再起をはかる自分の気持ちと本編を重ねてしまうことに対して、あまりにも突然の喪失を経験した本編やその先に見える実際の人々の大きな傷と自分の些細なつまづきは全く分けるべきなどと抵抗を感じる部分もあったが、作品内で徹底して「傷は比較するものではない」と強調されていたこともあり、そうして思いを寄せることに対して過度な罪悪感を抱くようなことはなくなった。
思いを寄せること、祈ることは何の意味も持たないと思う人がいるかもしれない。そんなことを言っている暇があったら募金しろ、というのも一理ある。十分な経済的支援がないと暮らしを立て直せるはずがない。しかし、募金は「募金する側」と「募金される側」を生む行為でもある。まったく別の世界に生きている人々ならまだしも、東日本大震災で傷を負った人々は同じ空の下にいる人々である。その主客関係が、共に未来へ歩んでいく妨げになることもあるのではないだろうか。そうした弱点を補ううえで、祈りは大きな意味を持ち続けると思う。
そもそも、このような祈りを無邪気に軽視すること自体「明日自分が生きている自信がない」「今日生きる意味をいちいち考えなくてはいけないほど苦痛に押し殺されている」そういう状況になく心身の面でも経済的にも安定した生活を送っているが故に出来る行為である。苦しい時であっても人として生きるために、頭の中にある最低限の理想と現実との隔絶といういつ自分が切り離されて奈落の底へ落ちていってしまうか分からない脅威に目を向けながらその隔絶をなんとかつなぎとめる、そんな闘いを無駄だ、自己満足だといって切り捨てることは、人が人として生きていくことの軽視であると思わざるを得ない。
「祈り」の意義は極めて大きいが、しかしそれは同時に、祈りにおいては皆がともに参加できる必要があるということを意味している。「皆」というのは生者だけではない。当然死者も含む。祈りにおいて排除された人々は、傷の先に描かれる未来を経験し得なくなってしまう。これはあくまで私見だが、当事者の傷はどれだけの時間が経ったかなど関係なく存在し続けるのにそれでもあえてあるひとつのタイミングを強調する意義はここにあるのだと思う。つまり、どんな時や場も常に祈りをする時・場として位置づけるのではなく、あえて限定することで、お盆やお祭りのように、死者を生者の世界に呼び寄せ、ともに祈ることを可能にしているというわけだ。
思いを寄せることを決して諦めないこと、死者とともに祈り、未来を見つめること。この1年間の経験の中で見つけたこれらの指針を胸に抱きながら、「震災後」を進んでいこうと思う。