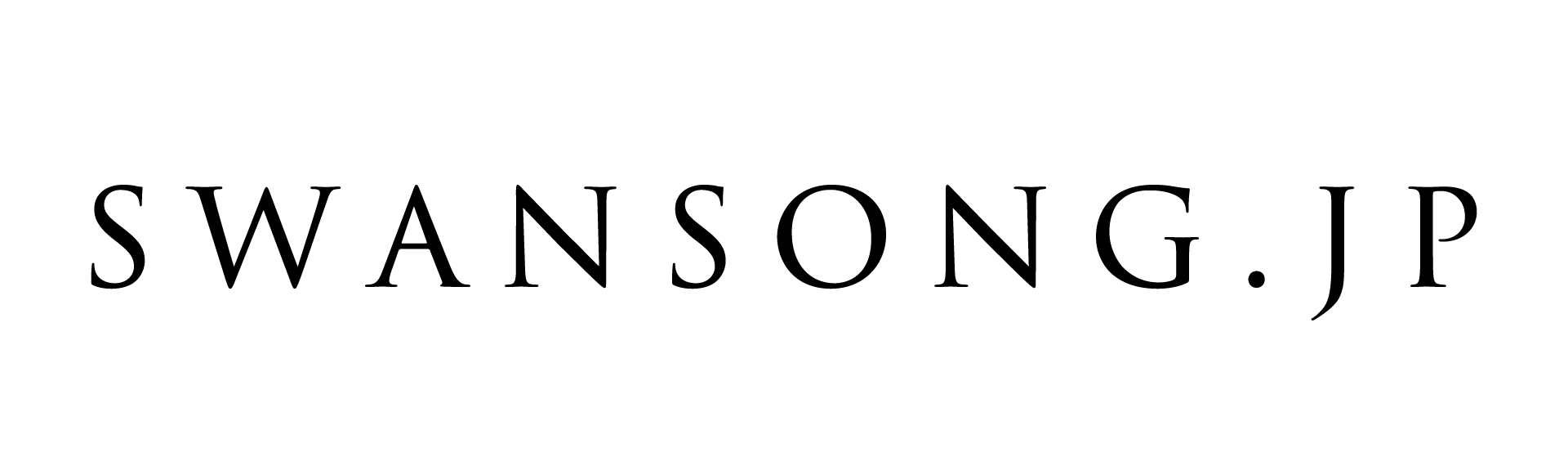2013年
最初に思いだすのは、2013年9月7日。時期で言えば、宮崎駿が「風立ちぬ」をもっての引退を宣言した頃だ。
その日行われるIOC総会中継を見るために、前の日から早起きする準備をした。招致レースではイスタンブールに差をつけてマドリードと東京が争う展開だとか、東京はあえて2回目の開催をする意味が問われているだとか、そんな報道がなされていた記憶がある。
しかし、テレビをつけた瞬間、表示されたテロップは目を疑うものだった。最終投票にイスタンブールと東京が残っているという。一次投票の結果を見る限りこれは勝てるのかもしれないと思いつつも、このIOC総会が福島第一原発汚染水問題報道の直後に行われたこともあり、いまいち確信を持てなかった。全員が起立して斉唱するオリンピック賛歌の長さにやや飽きを感じつつも、最終発表を待った。
当時のロゲ会長が喋り出したが、同時翻訳されているはずなのに内容が全然入ってこなかった。そうこうしている間に委員か何かの人から封筒が会長に渡された。自分ひとりしかいないリビングの緊迫感が異様に高まった。そして、午前5時20分。

2020年のオリンピック・パラリンピックの開催地は東京に決定した。IOC総会でのスピーチが話題になり、ちょうど運動会を控えていたため小学校では担任肝いりの企画でスローガン発表大会が行なわれた。「お・も・て・な・し」を真似るグループもあれば、その年の流行語大賞にもなった「今でしょ」を使いまくるグループもあった。自分のグループのスローガンはダダ滑りした記憶しかないので封じ込めたい思い出ではあるものの、あの時のお祭り感は凄まじかった。
招致段階から、自分の通っていた小学校には「今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ。」と書かれた横断幕が掲げられていた。まだ震災から2年半、政権再交代から1年弱しか経っていない時期。まだ「復興五輪」という言葉が説得力のあるものとして響いていた。物議を醸した「アンダーコントロール」発言ですら、当時は力強いリーダーシップの表れであるかのように感じられていた。というか、今もそう信じていたいとどこかで思ってしまう。

2011年
震災というのは、祖父がその前年末に亡くなり、2か月後に弟の誕生を控え、人生の中で最初に命と本気で向き合うしかない地点に立っていた自分にとって、他人事には感じられなかった。小学校の所見欄には、「震災について書いた作文でも、常に相手の気持ちになって考えることができる優しい心が育っていることがわかります」という文字が並んだ。震災の話は、小学校の卒業文集にも書いた。
「僕が二年生の時、東日本大震災が起こりました。それまで当たり前だと思う事もあった、身の安全。それが保障されていない現状、そして被災した人たちの辛い気持ちを実感し、『自分に何か出来る事は無いか』などと考えましたが、何よりも感じたのは、自然の恐ろしさというより、周りの人の大切さでした。この時から、僕は日常にこそ価値を感じていたと思います」
2011年というのは、個人的に大きなことが色々起きた年だった。学校で色々嫌な思いをして、窓枠に足を掛ける一歩手前まで行ったりもする中で、逃げるようにして勉強に傾倒するようになった。全国統一テストで上位を取ったことから自信もついた。中学受験をする意志を固めたのはこのあたりだった。在籍者が数名しかいなかったものの、受験指導塾でのコース分けは如実にヒエラルキーに反映されるようになり、4年生以降は徐々に嫌な思いをしなくなっていった。
また、俗にいう「エンタメの力」みたいなものを初めて感じたのはこの2011年に東京ディズニーシーで始まった「ファンタズミック!」を見たときだった。夏休み、当然人は多い。そんな中でかなり前から前の方に陣取って見たあの景色は言葉で言い表すことができない。学校生活に複雑な思いを抱える中で、こういったエンタメは「生きがい」を通り越して「生きる糧」だと感じるようになった。法的な制度が取りこぼした者でもエンタメなら救えると思った。今考えると、こういったエンタメへの信頼は、自分の辛い状況を理解してくれない周りの大人への不信感の反動とも言えるようなものだったようにも思える。
この年に生まれた弟は、僕がこうしてたくさんのことを書ける体験を得た9歳の時が、まさに2020年に当たってしまった。幼少期のうちに聴いていた音楽が将来の趣向にも関係するなどとよく言われるのと同じように、できるだけ幼いうちに色んな景色を見ておいた方が良いと自分は思う。エンタメの有するまっすぐさは幼ければ幼いほど受け入れやすいし、受け入れてしまえればその後拒否反応を示すことも少ない。こうなる前は家族でよく行っていたテーマパークなどでエンタメと出会える機会さえ奪われた弟にとって、オリンピックが大切な景色になれば…という気持ちはずっとある。それがオリンピックであるべきなのかという問いはありながらも、こんな時こそ大人が何らかの希望を見せなければ、子どもたちが未来を描くことはないように思う。
ミート・ザ・ワールドから文化祭展示へ
幼い頃から家にあった東京ディズニーランドのサントラCDがある。これにはいろんなアトラクションの音源が入っているのだが、ここに実際のパークでは聞いたことない、でもすごく好きな楽曲があった。「せかいのギコギコ?」などと今考えれば甚だおかしな聞き間違いをしていたが、正しくはこんな曲だ。この曲は「イッツ・ア・スモールワールド」や「There’s a Great Big Beautiful Tomorrow」など、ウォルト・ディズニーの生み出したアトラクションの軸となる曲を手掛けてきたシャーマン兄弟が作曲しており、訳詞を手掛けたのは少年隊「君だけに」の詞でも知られる康珍化である。
すべての人が笑顔絶やすことない
平和な未来を築くのさ 世界の友達と
手と手重ね 出逢うのさ 世界の人々と 愛を胸に
We meet world with love We meet world with love
(シャーマン兄弟による原詞)
Japan of today leads the way
Dynamic hopes and great dreams on display
And each year, our efforts increase
Touching all the world over with friendship and peace
Reaching out, friendly hands
To meet the world around us
Friendly people of Japan
We meet the world with love
We meet world with love We meet world with love
この曲は「ミート・ザ・ワールド」というかつてあったアトラクションの最後に流れるものである。日本史にハマっていた小学校高学年時代、ネットで調べ物をしていた時にこの「ミート・ザ・ワールド」のWikipediaを見て、日本の歴史を扱うこのアトラクションが一気に好きになった。
それ以降もこのアトラクションの存在は勝手に度々意識しており、中学生の頃にはDオタ界隈でよく叫ばれていた「現在のトゥモローランドは未来を見せていない」「『ビジョナリアム』や『ミート・ザ・ワールド』などの輝かしい未来を見せるアトラクションこそトゥモローランドに必要である」といった言説に辿り着き、それに賛同するようになる。「ビジョナリアム」というのは、ジュール・ヴェルヌやH.G・ウェルズが登場し、「未来に不可能はないのさ!」という最後のセリフが広く知られているアトラクションである。
そんな中で見たのが2016年公開の映画「トゥモローランド」だ。この映画では、「イッツ・ア・スモールワールド」がペプシ館として出展された1964年のニューヨーク万博がひとつの要素として描かれていた。徐々にネット漁りを深めていくうちに、「イッツ・ア・スモールワールド」にしろ、ネットサーフィンの成果として「ミート・ザ・ワールド」と関連性が深いという結論が出ていたEPCOTにしろ、このニューヨーク万博が鍵になることが分かってくるようになった。
そして満を持して迎えたのが2017年の文化祭出展である。ここでは「ジャニーズ舞台とディズニーパークの未来像」の話をした。ディズニーパークについてはここまで書いたことがその経緯だが、なぜ未来像というテーマにジャニーズ舞台を持ってきたのかという話もしておきたい。これもオリンピックに大いに関係するからである。
なぜジャニーズ舞台の「未来像」なのか
2016年夏にジャニーズJr.のファンになってからすぐの段階では普通にアイドルとして見ており、ミュージカル路線がこれほど大きな力を持っているということはまったく知らなかった。しかし、当時のMr.KINGの歌っていたメドレー(の違法動画)をYouTubeで見たことで忽ち方向性が変わってしまった。宝塚の男役のような歌声で平野紫耀が歌う「時計をとめて」、そして華やかなイントロで始まる「THE DREAM BOYS」は衝撃的だった。
その年の末から始まった「JOHNNYS’ ALL STARS IsLAND」はストーリーが難解…といえば聞こえがいいがハッキリ書くと支離滅裂で、ジャニオタ界隈でもジャニー喜多川の過去作と照らし合わせての解読が試みられていた。既にジャニーズミュージカルにハマっていた自分にとって、この解読結果を展示したいという思いが強くなった。「未来像」というテーマで揃えた訳はこの解読結果にある。当時のメモはもう散逸してしまったが、「子供対大人」「反戦」をテーマにしたこのミュージカルの指差す先は、明らかに東京オリンピックにあったのだ。展示では、ジャニーズ舞台の未来像をオリンピックとともに語り、ディズニーパークの未来像を万博とともに語った。そしてこの捉え方が、今に至るまで自分に強く根付いている。
もとはといえば、コンサート的なものとブロードウェイ由来のミュージカル的なもの、そしてラスベガスの噴水・電飾ショーのような華やかさが全部結合した「ショー」を好きになる土台というのは幼い頃にディズニーパークでたくさんのショーやパレードを見てきた部分にある。先ほど挙げた「ミート・ザ・ワールド」もジャニー喜多川が展開したショーも最終的にはオリジナル作品になっているとはいえ、(特に戦争や日本文化の描写において)往々にしてアメリカの視点での語りが混じってくるものであり、いかにも戦後的な日米関係の中で生み出されたことを特に隠すこともしていないエンタメと表現することもできる。この2つが結びつくのは、当然といえば当然であった。
リオ五輪ハンドオーバーセレモニー
ジャニーズJr.のファンになった頃と時を同じくして、地球の裏側ではオリンピック・パラリンピックが開催されていた。それぞれの閉会式の中で行なわれたフラッグハンドオーバーセレモニーには、度肝を抜かれた。(動画リンク)
ここでも、「ありがとう」の人文字で復興五輪が演出された。徐々にその危うさを理解してきてはいたものの、「日本に生まれてきて…」と思えるような演出だった。政治家を登場させるパートにやや引っ掛かりつつも、まだその時は見逃せていた。
こんな風に祭典をやるならば盛大にやるべきであると思い、国立競技場の縮小にも反発心があった。エンブレムでイチャモンを付けられるデザイナーを見るのも、正直しんどかった。一方で、デザインをしたいという興味は、このあたりから徐々に膨らんでいった。デザインをするようになってから振り返ってみても、(提出した写真の盗用がどうこうという部分は問題だが)経緯とコンセプトをちゃんと聞けば意図は分かるし、意匠それ自体が剽窃とはいえないと思っている。
パラリンピックの閉会式も良かった。招致決定当時はパラリンピックの存在を大きく意識したことはなかったが、当時まさに解散発表直後だったSMAPがパラリンピックのサポーターに就任していたことや、“発達に遅れがある”とみなされている身内がいるという当事者意識からか、関心を持つようになっていた。(動画リンク)
「パラリンピック」という名前の大会が初めて行われたのも、同一都市2回目のパラリンピックが初めて行なわれるのも東京だ、という事実に驚かされるとともに、“POSITIVE SWITCH”というキーワードに惹かれた。
よく、24時間テレビをバッシングする人がいる。もっともな意見も多いが、「知る」ことの価値、そしてコストを軽んじている意見も見られる。
1978年(昭和53年)、日本テレビ開局25周年を記念し、テレビの持つメディアとしての特性を最大限に活用し、高齢者や障がい者、さらには途上国の福祉の実情を視聴者に知らせるとともに、広く募金を集め、思いやりのあふれた世の中を作るために活用する、との企画意図で始まりました
https://www.ytv.co.jp/24h/igi_mokuteki.html
先程書いた“発達に遅れがある”子というのは、目で見ても分からないが故に、“落ち着きがない子”のように不真面目な子として叱らたり、公共交通機関で家族ごと冷たい視線を投げかけられることもある。しかし、決して本人の意思でそのように行動しているわけではないため、改善のためには地道な療養が必要になる。むやみにそういったグレーゾーンに位置する子を“ふつうじゃない”子として扱うことには異議を唱えるべき部分もあるが、名前をつけて理解を得て合理的配慮を受けなければ暮らしがままならない場合もある。それほどまでに切羽詰まるものであるという自体、なかなか理解が得られない。知らなければ、どうしようもない。東京都の作成したヘルプマークだって、未だに知名度が高いとは言いづらい。その意味で、24時間テレビは一定の役割を果たしているように思う。もちろん、テレビ的な見せ方のために、先ほど挙げたような内面的な障害を抱える子は取り上げられづらいという大きな問題はあるが。
少し話が逸れたが、パラリンピックでは、知ってもらうというだけにとどまらず、“SWITCH”というだけあって更なる価値観の転換を図れるのではないかという気がしていた。
本来であれば、先ほど挙げたような“弱さ”というのはひとりひとり何かしら持っているものであって、それを理解し合い、配慮し合うことが理想的な社会のあり方であるように思う。これ以来、東京パラリンピックには、その第一歩を踏み出すきっかけになる…とまではいかなくても、子どもたちにそういう社会が実現可能であるという希望の片鱗となる景色を見せられるという期待を持っていた。
ジャニー喜多川の死
「JOHNNY’S ALL STARS IsLAND」以降も、ジャニー喜多川はオリンピックに向けたミュージカルを世に送り続けていた。
明日に向かって旅立つ今
見上げる空は 深い蒼さのStage
ひとりひとり輝く命
やがて来る未来 すべて僕らのもの
ずっと探していた 本当の夢を
この手でつかもう 希望という輝き
夢に向かって ぼくら走り出そう
with us with love all 2020 Johnnys
Let’s start now
もう恐れないさ 僕らひとりじゃない
この思い世界中へ 2020 Johnnys
これは、2016年の「JOHNNYS’ ALL STARS IsLAND」以降毎年帝劇公演で使われていた「明日に架ける橋」という曲の歌詞の一部だ。
2017年には、東宝と松竹と合同会見を開いたこともあった。
平野は「3年後のオリンピックでは海外から多くのお客様がいらっしゃいます。日本のエンターテインメントの中心地である銀座と有楽町から僕達にしかできないエンターテインメントをお届けしたい」と掲げた。
https://www.oricon.co.jp/news/2096177/full/
2020年の東京五輪を控え、銀座・丸の内・日比谷エリアのさらなる活性化・街づくりを見据えて2社の連携によって開催された同イベント
https://www.oricon.co.jp/news/2096177/full/
2018年には、一度消えかかっていた「Twenty Twenty構想」を再度発表し、こんな夢も語っていた。あくまで劇場での盛り上げを図るジャニー喜多川の考えは、「現政権下では政治色が強くなるのではないか」と年々個人的に危惧の度合いを強めていた開・閉会式と一定距離を置いているという意味で自分に好都合なものだった。その当時には、ベルリン五輪という暗い過去をうっすら理解するようになっていたが、それでもかろうじてオリンピックの役割は信じていた。
2020年、外国からもたくさんの方が来られる。その時に彼たち40人が、いろんな劇場でパフォーマンスして、日本のすごさをお見せできたら楽しいですよね。今の子たちなら、できる。
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201810070000012.html
平和の祭典としてオリンピックを華々しく描き続けるジャニーズミュージカルはずっと自分が大切にしてきたエンタメの理想(「ミート・ザ・ワールド」はまさにそう)とまさに合致するものだった。また、そのミュージカルに浸っているうちに、オリンピック反対に傾きがちな周りの大人とは違う“何かを信じ続けている数少ない大人”としてのジャニー喜多川の描く2020年への期待と自分自身の抱く2020年への期待が徐々に重なって見えるようにもなった。「信じ続けていい」とジャニー喜多川に言われているようでもあった。
しかし、ジャニー喜多川は、2020年を迎えることなく亡くなった。東京オリンピックまであと1年というところで頭痛を訴えて倒れ、くも膜下出血で天に召されたジャニー喜多川の無念さは、計り知れなかった。同時に、それは自分にとってオリンピックを希望あるものとして描き続ける作り手の喪失を意味してもいた。東京ドームで行なわれたお別れの会では、不思議なほどに涙が止まらなかった。
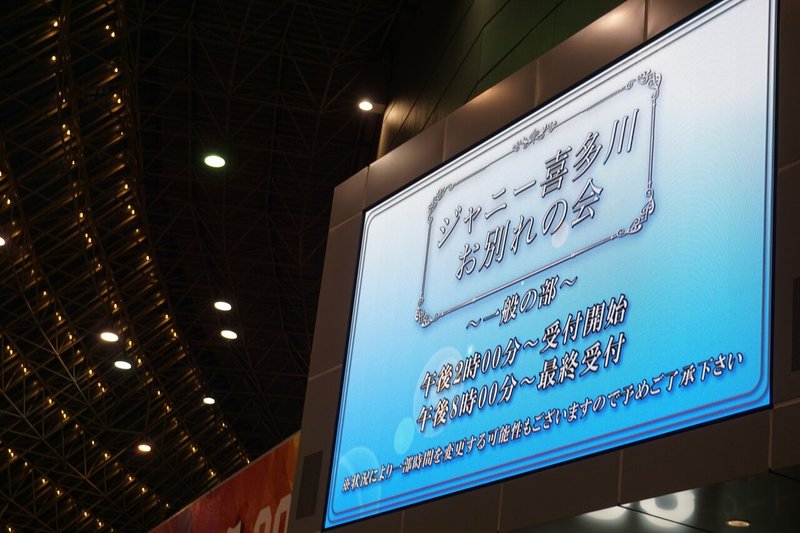
9月に上演された帝劇ミュージカル「DREAM BOYS」では、ジャニー喜多川の生前の意向もあって、「立ち止まることより一歩先で倒れることを選ぶ」と歌う曲が物語の軸に追加された。“Show must go on”がジャニーズ事務所の社訓のようなものになった。輝かしい未来を目指してエンターテイメントを諦めず、何があっても立ち止まらず進み続けることが、ジャニー喜多川の想いを受け継ぐことそのものだと思うようになった。
「いざ2020へ!」
ジャニー喜多川が亡くなったという大きな失意の中でも、彼が楽しみにしていたオリンピックそのものはある、と希望を見出すことも出来ていた。ちょうどジャニー喜多川が倒れ、亡くなったのが開幕1年前の夏だったという事実が、ここでは良い方向に働いた。
ジャニー喜多川が倒れてから亡くなるまでの祈るしかない期間中に、オリンピックチケット当選結果発表と払込期限があたっていた。新競技スケートボード、そして久し振りに復活する女子ソフトボールのチケットが取れた(画像は延期後)。


7月には工事が進んでいた国立競技場へも行った。

展示されるメダルを見るために朝から都庁に向かって長い列に並んだこともあった。学校では、いつもオリンピック柄のタンブラーとペンケースを使った。
12月に入り、ジャニー喜多川が亡くなってから初めての「JOHNNY’S ALL STARS IsLAND」シリーズの公演が始まった。ジャニー喜多川との思い出を語るシーンが新たに追加されたが、オリンピックを輝かしいものとして描く根幹の部分は変わっていなかった。
そして迎えた2019年12月31日。NHK紅白歌合戦では、MISIAがレインボーフラッグを持って歌い、氷川きよしは紅組・白組という型から解放されたパフォーマンスを行い、嵐は「父は言った『逃げていい』」と歌うオリンピックソング(動画リンク)を披露した。
「もしかしたら、本当にこの国は変われるのかもしれない」と思った。大トリを務めた嵐の曲名の上に表示されていた「いざ2020へ!」の文字に心が躍っていた。オリンピックというものが大きい存在として演出されればされるほど、またオリンピックが本来“強さ”を求めるものであるとされてきたという過去が強調されればされるほど、オリンピックを内側から彩るエンタメのあり方が変われば社会全体にとっての変革を生むきっかけになると思った。弱さは悪じゃない、“普通じゃない”は変じゃない、と言える社会になると思った。薄々オリンピックに政治の影を感じつつも、そう確かに信じていた。
この月には、中高6年間の集大成としての新体制が始動していた。文化祭の歴史上、69回中2回だけというオリンピックイヤーの文脈が最大級に活きた、祭典らしい祭典にしたいという気持ちがあった。ジャニー喜多川が亡くなった今、オリンピックを重んじるそのスピリットを継ぎたいという気持ちもあったのかもしれない。同時に、高3自ら従来の枠組みを改め、2020年代にふさわしい文化祭のあり方を提示したいという願いもあった。
2020年
しかし、そう上手く事は運んでくれなかった。
「今年、東京にオリンピックがやってきます!」と出演者が満面の笑みで語る「JOHNNYS’ IsLAND」を自分が見に行ったのは、1月14日のことだった。このミュージカルのもう一つのテーマは、「ジャニー喜多川が生前良く言っていた“Show must go on”の本当の意味」であった。2幕の最後にはこんな言葉もあった。
そして今、宇宙船が帰ってきました。あの宇宙船には、僕たちの未来が詰まっています。実はこの演出は、6年前、東京オリンピックが決定したその翌日にジャニーさんから教わっていたものなんです。でもその内容は、宇宙船からたくさんの子どもたちが現れる、というところまでです。ここから続きのエンターテイメントは僕たちの手で作り上げていきます。
子供は大人になれるけど、大人は決して子供に戻れない。その意味を噛みしめて、僕たちは目一杯今を生きよう。
鑑賞翌日、1月15日に新型コロナウイルスが国内で初めて発見された。“Show must go on”は仮想の言葉になった。それ以来、一年以上ジャニーズの現場には行けていない。「いろんな劇場でパフォーマンスして」と晩年のジャニー喜多川が語っていた2020年の夏には、劇場が閉ざされていた。
Twenty Twentyは、若者の希望が生まれる祭典としてのオリンピックにふさわしく、ジャニーズJr.40名によって結成される予定だった。しかし、ジャニー喜多川亡き後の新体制は、その構想名を使ってデビュー組によるチャリティーユニットを結成し、「遺志の継承」を謳った。一番ジャニー喜多川に近いところにいたはずの新体制がその思いを蹂躙するような道を選んだことが、信じられなかった。
もはや忘れられているが、2020年2月末、一番最初に自粛を要請されたのはエンタメ業界だった。エンタメが一番輝くはずの年なのに、まっさきに切られたことが許せなかった。「文化の灯を絶やしてはなりません」という政治家の言葉の空虚さに耐えられなくなった。
東京ディズニーリゾートは、4か月にわたる長期休業に入った。エンタメに没入するきっかけになった「ファンタズミック!」はこの影響で当初の予定より早く終演を迎えてしまった。小3の自分を救ってくれた演目の最後を見届けることは叶わなかった。
それから間もなく、休校になった。直接会えなければ、話せなければ、前に進めることも難しくなる。やることに対してではなく、人格を否定するような悲しい言葉を目にすることも増えた。小3の時のような感情がよぎることもあった。でも、鋭い言葉だって、苦しい状況にあるが故に出てきた言葉かもしれない。ただでさえできるか分からない状況下なのに新しいことをやろうなどと希望を語る方が悪いという気持ちも芽生えてくるようになった。
これに限らず、あらゆる側面において、新しいことができる、型から脱出する契機なはずの年が、与えられた檻の内で頑張り続けることを求められる年になってしまった。気が付けばオリンピックは延期になっていた。ずっと楽しみにしていた2020年は消えてなくなった。
エンタメの役割という点をみても、社会のあり方を問い直したり、価値観をじわりじわりと変えたりすることより、「貢献」することが優先されるようになった。震災後、多くの音楽番組が「音楽の力」に類する言葉を並べたのと似ている。「応援」といっても、それこそ「カイト」にみられたような弱さを認める応援の仕方ではなく、強くあること、自分の願望を抑え込むこと、また悲しみを乗り越えることを善とするような「応援」の仕方がよくとられるようになった。前述のTwenty★Twentyが歌ったチャリティーソングでは、この時代の悲しい出来事が暴風雨で散乱したゴミに準えられており、サビでは「けりをつけなくちゃね その悲しみに」というフレーズが使われていた。
ジャニーズは「価値観を変革する未来のスタート地点」や「若者の希望となる」2020年を描いてきたはずで、それはオリンピックがなくなったとしても継続できるものだという自分の気持ちと、今2020年にジャニーズの歌うチャリティーソングの趣旨があまりにもズレていることが、ただただ悲しかった。身の回りの人を突然失って悲しんでいる人が確かにいる中で、なんでそんなことをチャリティーソングとして歌えるの、と何度も嘆いた。怒りという感情が浮かぶような元気さは既に失われていたし、これまでずっと信じてきたものは最初からただの幻想だったのかもしれないという思いすら湧いて来るようになった。
ジャニー喜多川の一周忌を前にして、大きく体調を崩した。これがとどめになってしまった。夏には学校をやめることも何度も考えた。このまま死ねるなら死んでもいいと思った。少しでも快復するためにエンタメに満たされた空間に身を置いてみようと考えても、もしかしたら自分は家庭内で感染しているのかもしれない、そうだったら迂闊に外に出るのはナイフを振り回していることと何ら変わりはないのだと躊躇することが増え、せっかく意思を固めて映画館に行ってもどうも集中できずに上映が終わってしまう経験が増えるようになった。 「自分の生は常に誰かの犠牲を伴ってようやく成り立つものである」という 中学受験での合格以降の想いがより強まり、自分のために誰かを傷つけることを嫌がる気持ちが勢いを増した。
エンタメを享受するうえでのブランクも恐怖に変わった。映画やショーを観た後の心が洗われる感覚こそが、ここ数年ジャニーズミュージカルが描いてきた「純粋な幼心をもって生きていく」こととほとんど等しいと思っていただけに、この成人間近というタイミングでそういったエンタメを見ないブランクが出来てしまうと、年々薄れつつあり鑑賞頻度を上げることでかろうじて意識の中にとどめていたあの感覚が一切つかめなくなった状態で大人になってしまうのではないかと怯えるようになった。18歳で迎える2020年のオリンピックとはまさに、「あの感覚が一切つかめなくなった状態で大人になってしまう」ことを防ぐために一番いい時期だと思っていた。でも、その真逆のことが起きている。2020年を信じすぎていたがために、いちいちすべてのことに「2020年なのに」がついて回り、自分を苦しめた。
そして、こういった傷を掬いあげてくれたのが、堂本剛の言葉と音楽だった。6月にラジオで堂本剛が発したこの言葉は一生忘れないと思う。
天災が起きたときもそうですし、こういった世界的な問題の中でのこういうそのなんて言うのかな、思いやることとか、与えることとか、救うことみたいなことって、なに正義ぶってんのみたいに言われたり、なんか考え子どもじゃない?みたいな感じで言われたり、なに変に熱くなってんのって言われたり、いっぱい傷つくよねぇ。いっぱい傷ついたし。え、なんで?って、そのそれこそ今でいえば医療従事者の方々に対して、本気で何で思っちゃいけないのって思ったりするし、今の生活支えてくれてる人たちもそうだし、こうやって支えてくれてるファンの人たちに対してもそうだけど、なに熱くなってんのみたいな、いや熱くなるでしょって思っちゃうし、でもなんかこういう時って本当に人であることに悲しくなる瞬間もすごくあるっていうか、なんで人ってこうなんだろう、みたいな。いや本当にそうやって思っているから言っていることが何でダメなのっていう。なんかその、そういう風に純粋な気持ちでこういう問題に対して向き合うことへの嫉妬なのか何なのか分からないけど。そう思わないならそう思わないって言えばいいじゃないっていう、なんか思ったりもするんですよね。
こういうものに対してちゃんと向き合った考えを持つことがあたかも“ダサい”振舞いであるかのような空気には相当違和感があって、それを綺麗に言い当ててくれた感じがした。
「SONGS」に出演した時に、KinKi Kidsの活動とは異なるソロの音楽活動でファンクを取り入れるようになったことについて、「『今すぐ立ち上がれ』とか『生きてる人々すべてがスターなんだよ』とか、なんかそういうメッセージが多いものにたまたま最初触れたんですよね。そういう躍動感、人が生きているっていうことが鳴ってるものを聴きたかったんだぁって」と語っていたりとか、ジャニー喜多川に向けた追悼歌「You…」を制作した際に近年のジャニーズミュージカルを見ていないはずなのにそれらの作品に見られるような言葉を使っていたことから、堂本剛はジャニー喜多川に近い感性を持っている人なのかもしれないという思いはもともとあったことにはあった。しかし、しかしである。
You…
愛してるよ きみが観てる景色を
どんなに離れてしまっても
遠ざかる未来(あす)を 見送る僕に変わって
叶えられるよ 君ならWe’re the ones… 歌おう
世界は君のステージ
ひとつも恐れることはない 悲しむことはない涙の虹を それぞれの今日へ渡そう
歩いていこう 僕らの
We’re the ones…
You… 君の愛を 君のすべてを そこに信じて 捧げよう そっと
愛が必要と 愛などいらないよと 争う そこに放とう
We’re the ones…蒼い船で 待ち合わせて 僕ら 命(たび)へ出た
奇跡の果て 廻り合った いまを 愛そう…You… 思い出して 幼い日の心を 美しい瞳の自由を
「You…」(詞:堂本剛) より
誰もが未来(あす)を 知らない夢をみてる
叶えられるよ 僕らは
We’re the ones…
さすがに、今まさに起こっている問題に対してこのような考えを持つ人が芸能の世界にいるとは思わず、かなり驚いた。
どれだけ言葉を尽くしても究極的に自分以外の人を大切にできないという人間の弱さ、そして旅立っていった人たちへの想い、いつか人間皆が愛を持って和解の境地に達することができると信じる気持ちが歌詞に込められた楽曲「新しい時代」(作詞:堂本剛)も、無配慮が目立った例のチャリティーソングとは対照的なものとしてすっと腑に落ちた。この曲こそが、あの2020年が消えてなくなったという現実に対する最適解だと思う。
自分が大切で悲しくなるんだよ 愛しているよきみを…
嘘ひとつないのに… その矛盾に揺れてる
旅立った命(うた)たち 鳴き止まない惑星(ほし)で
こころに咲く 手を繋ごう
信じているよ 涙目に浮かべた
この地球(ふね)が 愛に着くのを…
同時期に、課題研究の関係で調べていた石牟礼道子(高い共感性から「もだえ神」とも呼ばれる)の言葉にも、堂本剛と同じく“罪を犯してしまう”他人に対してどうこうというより、自分も“こんな罪を犯してしまう人間”であることが悲しいだとか人間として生を受けたことに虚しさを覚えるとかいう、原罪意識にも繋がるような発想があって一気に引き込まれた。
この日はことにわたくしは自分が人間であることの嫌悪感に、耐えがたかった。釜鶴松のかなしげな山羊のような、魚のような瞳と流木じみた姿態と、決して往生できない魂は、この日から全部わたくしの中に移り住んだ。
「苦海浄土」より
こういうものに対して共感を覚えてしまうほうだから2020年を信じすぎていた部分はあるとは思いつつも、こういうものに出逢えたのは確かに幸運だった。
岡本太郎と祭り
消えてしまった2020年の裏で、微かに続いた光もあった。映画「トゥモローランド」以来の万博趣味である。
コロナ禍になるずっと前、2019年の関西地域研究では、自分の強い希望で太陽の塔の内部見学に向かうスケジュールが決まった。

当時のまま残っていた「The future, WORLD of progress」「進歩の世界」という看板を見て、ニューヨーク万博との連続性、その時代特有の価値観を感じるとともに、従来の万博イメージを覆し、土着性を漂わせる岡本太郎の世界観に圧倒された。
時が経って、2020年2月の休校発表時には岡本太郎のこの言葉がよぎった。
生きる瞬間、瞬間に絶望がある。絶望は空しい。しかし絶望のない人生も空しいのだ。絶望は、存在を暗くおおうのか。誰でも絶望をマイナスに考える。だが、 逆に強烈なプラスに転換しなければならない。絶望こそ孤独のなかの、人間的祭りである。私は絶望を、新しい色で塗り、きりひらいて行く。絶望を彩ること、それが芸術だ。
4月になり、暫定的にデザインをすることになった際によぎったのは大阪万博の文脈だった。オリンピックイヤーの文脈が活きなくなったとしても、2025年の関西万博に向けて50年前の大阪万博を引用すれば、祭典を祭典らしく彩ることができるだろう。そこで、大阪万博関係の写真を見て目に留まったソ連館をモチーフにデザインした。
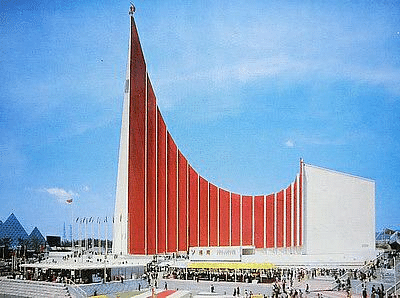
時が流れ、7月に正式に自分がデザインをすることになった。そこで着目したのは、岡本太郎が大阪万博で表現した、呪術性を帯びた「祭り」の姿だった。天然痘の流行という社会背景もあって建立された奈良大仏のように、祈りを捧げる場としての祭りのシンボルを描くことを目指した。
「祭り」は根源の時代から、人間が絶対と合一し、己を超えると同時に己自身になる、人間の存在再獲得の儀式である。
また、時は遡って春の頃、新しいことを始める流れの中で「お祭り広場」という名前に着目する機会があった。それからというもの、大阪万博に同名の広場があることと何らかの関係性があるのではないかとうっすら考えていたが、いまいち確信を持てずにいた。が、9月になって偶然そこに関係性があることを知る機会があり、創立40周年記念誌を読んでその確証を得た。岡本太郎的なものをテーマにしたいという自分の考えと、広場が静かに秘めていた大阪万博の文脈がここではっきりと繋がった。はっきり言って奇跡と呼べる瞬間だった。
この偶然の合流もあったからこそ、なんとか11月まで走り続けることができた。体調のこともあり、どうしても心残りはあるものの、2020年らしい祭典の文脈を…という当初の願いはかろうじて叶った。他にも予期せず叶った目標があり、「捨てる神あれば拾う神あり」を極端な形で感じた活動だったように思う。
「オリンピックイヤー」
2020年末に「今日もテレビで言っちゃってる 悲惨な時代だって言っちゃってる」がこんなにも響くと、誰が想像しただろうか。第二波、第三波と続く最中、2020年12月31日を迎えた。嵐活動休止前最後の日である。ふと無念さを滲ませる5人の姿に、ついついこの一年見てきた記憶の中の景色を重ねてしまった。嵐がいなくなる寂しさと、2020年という困難の年まで嵐がそこにいてくれた感謝と、いろんな思いが自分の中で交錯した。こんなに泣く大晦日はもう来ない、と信じたい。
2020年に期待しすぎていたために、2021年の年明けに自分はうつ病患者になった。2020年の間走り抜けたことで気持ちが緩んだのか、いつなされてもおかしくないオリンピックの中止宣言時に自分がどうなってしまうのかという恐怖があったのか、以前ほど治療へ入ることに躊躇がなかった。しかし、そうしてようやく道を外れてしまったことを認められるようになってからも、いつまで病人なのか、ずっと夜が明けないまま自分の手でその幕を閉じてしまうのではないかと別の恐怖が襲ってくるようになった。
年明け早々緊急事態宣言が再発令された。政治家は、年末年始にも「打ち勝った証」として五輪開催を進めようとしていた。復興五輪という言葉は、とっくに忘れられていた。クリスマス2日前には、開・閉会式の演出メンバーが変わった。開催まで半年強となったこのタイミングで変えたことが信じられなかった。他国開催のオリンピックよりずっと政治色が強くなるという危惧が現実のものとなった。
そんな中で、組織委員会会長の差別発言があった。度々失言をしており、開催をマイナスの方向へ傾けているようにしか思えない会長だったから、もはや何も思わなかったし、思わなくなってしまったことが悲しかった。その瞬間、オリンピック憲章に沿ったオリンピックが実現すると信じることをもう自分が諦めたのだと気づいた。
もちろん中止になったらジャニー喜多川が亡くなった時に匹敵する喪失感に襲われるんだろうし、それを予期したことがうつの治療を決めたの要因ともなったとはいえ、今この状態でオリンピックが開催されたとしても…という思いもまた出てくるようになった。外国からの人の出入り自体が難しい今開催されるオリンピックの意義は限りなく不明瞭である。
これを書いていて思い出した言葉がある。最初の自粛要請が出る数日前に発表された東京2020大会スローガン、“United by Emotion”だ。よりによって、これがスローガンだったのだ。
会わなくとも会話ができる時代に、
東京に、世界から人が集まる。
世界は、これほどまでに国も人種も文化も世代も、
多種多様な人間でできているのか、と戸惑うかもしれない。
しかし、その異なる私たちは、
アスリートの肉体や勇気や挑戦を共に目撃し、
心震わせ、笑い、泣き、拳をあげるだろう。
そう、人と人は明らかに異なり、
しかし間違いなく同じなのだ。
私たちが共に抱く感情が、壁の向こう側を想像する力になり、
互いを区別するものを超えてゆく力になる。
人は、時間と場所を共有することで
共に生きる意味を見つけるのだ。
人間は人間がいる光景から
未来への大事なことを知る。
言語を超えて感動を分かち合える瞬間にこそ、オリンピックのもつ平和の祭典らしさが表れる。ジャニー喜多川が創ってきたショーはよくおもちゃ箱をひっくり返したようなものと評されるが、それもまた言語を超えたものだからこそ高い価値があるのである。同じ空間で感動を共有する体験がないオリンピックは、果たしてオリンピックなのだろうか。
しかし、そのような思いは、東京が2016年大会都市選考に落選して、その後2020年大会に再度立候補した時から10年ぐらいにわたって自分の真ん中に近い場所を占めてきた「東京オリンピック2020はきっと良いものになるはずだ」という信念にひとつの区切りを打つことにもなりかねない。2016年大会招致用に作られた水引エンブレムのシールを帰りの会で配られたときの記憶や、それから10年後静かに胸躍らせた「カイト」の「憧れた未来は 一番星の側にそこから何が見えるのかずっと知りたかった」というフレーズがふと頭をよぎる。これは、自分の器では抱えきれないほどに難しい、現在進行形の問題である。
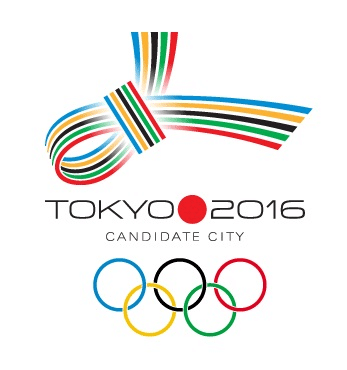
おわりに
「痛みを知らないと他人の傷に寄り添えない」本当はそんなことを言いたくない。痛みを知らなくたって、傷に寄り添えるはずだ。痛みを知らずとも傷に寄り添ううえで、この上ない手助けをしてくれる存在こそ文化芸術だといまだに信じている。
でも、傷つけば傷つくほど、さらに傷ついている人の存在を意識するようになったのも確かだ。いわゆる「坑内カナリア芸術論」のように、弱さを持っているからこそ、社会の歪みやヒビに気づくことができる。そう思うようになった。
強くなったぶんだけ、自分の痛みや他人の痛みに気付けなくなるのは嫌だ。柔らかい心を失う事が強さなら、弱いままで良い。
「ぼくの靴音」 ( 堂本剛 エッセイ集)
ジャニーズミュージカルの代表作「Endless SHOCK」のセリフ「俺たちはひとつ苦しめば、ひとつ表現が見つかる。ひとつ傷つけば、またひとつ表現が作れる。ボロボロになるその分だけ輝けるんだぞ」のように、傷つけば傷つくほど不思議なほどに表現の幅が着実に広がっていくことも実感した。表現の幅が広がっている実感がある中で表現に携わる役職を務めることになったからこそ、走り続けられた部分も確かにあった。
一方で、こんな思い込みをしてしまうようになった。あの時点でジャニー喜多川が亡くなったのは本人にとって良かったのかもしれない、現代日本にオリンピック精神を体現することなど最初から無理だったのかもしれない、と。そんなことを思いたくはないのに、そう思ってしまう。そうでも思わないと、とても暮らしていけない。夢を見た過去を否定しないと、夢を見られない今を生き抜けない。「希望溢れるオリンピックなんてただの思い込みだ」という考えがよぎってこれまでの自分を信じきれないことが、悲しい。エンタメにのめり込むきっかけともなった大人への不信感が、再び大きく膨れ上がるようになった。
それでも、2020年に描かれるはずであったものの存在自体は信じていたいと思ってしまうし、こうやってまた2025年の関西万博に期待してしまうんだろう。期待した先に、1970年時にはあり得なかった政治色の強さにうんざりする結果があったとしても、それでも信じていたいと思う。
序盤に挙げた「ミート・ザ・ワールド」には、このようなセリフがある。
これからは、あなたたちの時代よ。あなたたち、あなたたちの家族、そして友達、みんなで一緒になって未来を創っていくのよ。
人々の英知と努力、そして外国との数々の出会いを通して日本は大きく育ってきたわ。そして未来は…そう。これからは、世界中の人々とお互いの文化を理解し分かち合い、平和で心豊かな世界を築き上げる時よ。
日々の積み重ねだけでは、日本のエンタメはいつまでたっても旧態依然のものでしかないし、日本の社会は“気づく”側に回ることはできないと思う。世界と出会うことで生まれる、真の“POSITIVE SWITCH”がこの国に訪れることを祈りたい。ただ祈るのではなく、本来は日々の進歩に貢献する者でもありたいところだが、今は祈ることしかできない自分の脆さを自覚していたい。オリンピックの開催が絶望的になった今、うつ病患者になった今、そんなことを思っている。